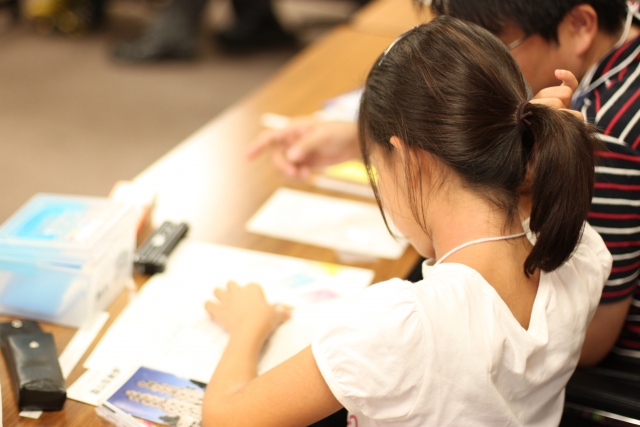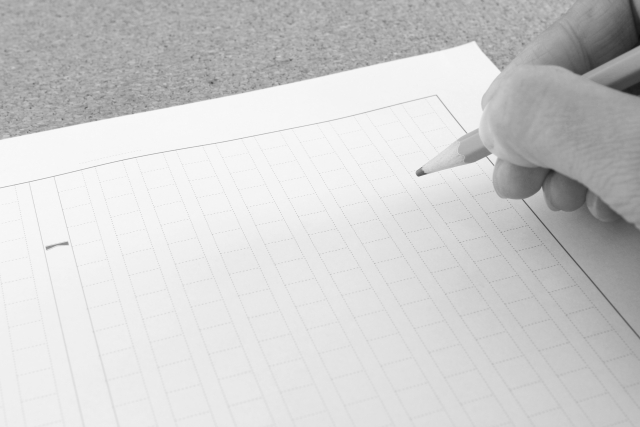2020年の教育改革の内容を見ても、これから子どもの教育は、今までとずいぶん変わりそうです。
アメリカを拠点に20年以上教育に携わり、4,000人超のグローバル人材を輩出したきた、船津徹氏の著書「世界標準の子育て」に関する記事ありましたのでご紹介。
「世界標準の子育て」では、4000名のグローバル人材を輩出してきた著者が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を紹介していく。
その、子どもの将来を決める「たった一つの条件」というのは。
子どもの将来は、「自信」の有無で9割決まる
自信があるかないか。このたった一つの要素によって、子どもの学力、コミュニケーション能力、メンタルタフネス、その他の特技などの伸び代が大きく変わってきます。
困難に負けないチャレンジ精神、挫折を乗り越える気持ちの強さ、円滑なチームプレイを可能にさせる社交性、より難易度の高い技術や知識の習得、自分の頭で考える力などなど、あらゆる要素を支えるのが子どもの自信です。
子育ての90%は、「自信育て」に左右されるといっても過言ではありません。
「自信」というのは、「自らを信じる」
子どもが、「自らを信じる」ことができるように育てる必要があるということですね。
2種類の自信、「根拠のない自信」「根拠のある自信」
では、具体的に自信を育てるとはどういうことなのでしょうか。
そもそも自信とは、2つに分けられます。
一つが、「根拠のない自信」
。blockquote>「根拠のない自信」とは「自分は親に愛されている」「自分は親から受け入れられている」「親から大切にされている」という自信であり、「自分は価値がある人間だ」と子どもが自分の存在を心から信じている状態です。
となっていますが、「根拠のない自信」でなく「与えられる自信」といったほうが判りやすいと思います。
子どもがいくら努力しても手に入れることはできません。子ども時代に親からかわいがられ、大切にされ、愛情をたっぷりもらうことでのみ得られる自信なのです。「根拠のない自信」はすべての土台になります。ここが大きく安定していれば、その上に積み上げていく勉強、習い事、人付き合い、あらゆることがうまくいくようになります。
「根拠のない自信」というか「与えられる自信」の方がしっくりくるかと思います。
後半の部分に関しては違和感を感じる部分もありますが、まずは、親が子どもを信じてあげることが、まずは子どもの自信ですね。
子どもを信じて、愛情を注ぐことが基本。
でも、それに加えて
もう一つが、「根拠のある自信」
たとえばスポーツ、音楽コンテスト、発表会に出て人前でダンスや演劇を披露したりと、競争にもまれながら一つのことを継続していくことで得られる自信です。
親は、子どもが「根拠のある自信」を獲得していくために精一杯のフォローをしていくことが重要になります。
習い事をするなら野球よりウインドサーフィン!?で書いたように、「鶏口となるも牛後となるなかれ」
どんな分野でもいいので、「一番」だと、親以外の他の人から認められることが、自信になるんですよね。